でっちあげ~殺人教師とよばれた男

「でっちあげ~殺人教師とよばれた男」という映画を見た。教室で指導した些細なことを子どもが親に自分の都合のよいように話をし、それを100%信じた(自分の中で1000%くらいに膨らませて)教師や学校に感情的に捩じ込んでくるモンスターペアレントが話の発端の実話を元にした映画。自分を敵視する保護者、事なかれ主義の管理職、センセーショナルな話題に喰いつくマスコミ、社会からの批判を恐れる教育委員会。こういうことは教育現場にいると全てリアリティーがあり、自分も似たような経験があるので、他人事に感じられず、柴咲コウが演じる母親がとてもリアルに見えてゾッとした。(それだけ演技がうまいということだろう)
母親は涙で感情的に、父親は怒声で威圧し、教師を攻撃する
ちょうど、この映画の元になっている福岡での事件があったころ、自分自身も、ある日の夜10時過ぎ、自分の自宅にクラスの生徒の母親から電話があり、揉めたことがある。話を聞くと、生徒が自分に都合のよいように事実を捻じ曲げた話を信じ込んでいる。いくらその話が事実と異なっていることを説明しても、最初から感情的に泣きながら話をしていて聞く耳を持たず、ヒステリックに同じ話が繰り返されて1時間以上たっても納得しない。シングルマザーのはずだが、途中からべらんめぇ調の輩のような話し方の男に電話が変わり、最後は「明日、学校へ行くからな、オマエ顔を洗って待ってろ」と脅され、自分も「顔は洗わないが、待ってるからいつでも来い、馬鹿野郎」と言って電話をたたき切ったことが・・・。
自分はADHD気質なので、特に男性からこのように喧嘩を吹っ掛けられるとアドレナリンが出て、こういうことを言ってしまう(他にも何度かあり・・。反省)のだが、ほとんどの教師はこんなこと言えないし、言ったこともないだろうと思う。また今よく考えると、この電話での会話の内容が録音されていて、自分の最後の言葉だけを切り取って週刊誌などに話を持っていかれると、映画のように「暴言教師」「いじめ教師」などとセンセーショナルに報道されてしまう可能性もある。さらに今はSNSもあるのでそこで関係のない人の変な正義によって無茶苦茶騒ぎになるかもしれないと考えると恐ろしすぎる。
この話は自分の対応で完結したので、自分の言い分を全部吐き出すことができたが、これが管理職や教育委員会が絡むとこれまた、自分の自由な発言は禁じられ、当然、マスコミにも反論できなくなることが予想できてしまう。
福岡の冤罪事件の問題点
少しネタバレになってしまうが、映画を見て、このケースの問題点を整理すると、
1 最初、問題を大きくしたくないために、担任がこどもと保護者の言い分を認め体罰の件を謝罪してしまったこと
2 管理職が問題を大きくしたくないために、保護者の言い分のみを鵜呑みにし、よく調査せずに問題の責任を教師に押し付け解決しようとしたこと
3 新聞や週刊誌がよく事実確認もせず、保護者の言い分のみをセンセーショナルに記事にし、実名報道したこと
4 教育委員会は、学校(管理職)からの報告に基づき、教師の言い分には耳を傾けず、マスコミや世間から批判を恐れ、停職60日の懲戒処分にしたこと
教師はどうすればよかったのか
1 保護者が学校に体罰の被害を訴えてきた時に、体罰の定義を調べ、当該行為が体罰には当たらないことを管理職や保護者に主張すべきだった
2 それでも、体罰だと学校側(管理職)が決めつけるのであれば、その時点で弁護士に相談して学校側と争う姿勢を見せ、他の生徒などへの調査を求め事実を争うべきだった
3 週刊誌と保護者に対し、記事の内容が事実無根であると、名誉棄損の訴えを起こし、自分の言い分を主張する場を自分でつくらなくてはいけなかった
4 自身の任命権者(ここでは県)の人事委員会に不利益処分に対しての不服申し立て(実際にもやっていたと思うが、相手に裁判を起こされた後ではなく即座に行うべきだった)を行う
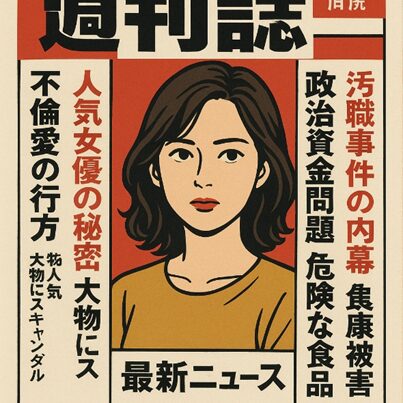
明日は我が身
いずれも学校側が事なかれ主義で、とりあえず保護者側の要求を飲み、謝罪することを自分に求められた場合、自分の味方は誰もいなくなり、孤立無援の状態に追い込まれる。この時に冷静に判断し、学校側をも敵に回して学校や教育委員会、保護者とも戦うのは相当な勇気と覚悟が必要。教師が保護者を訴えるという事例は過去に数件しかなく、早い段階で戦う覚悟を持つことはとても難しいことだと理解できるだけに、こういうことは誰にでも起こる可能性があり、「明日は我が身」の怖さがある。
法的対応の重要性
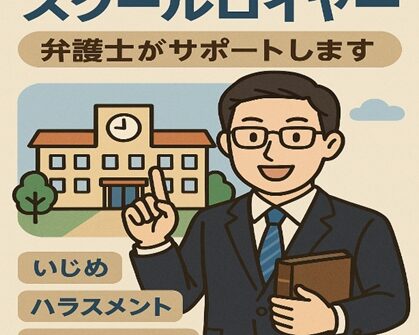
ただひとつ言えるのは、保護者が威圧的な態度で、過剰な要求をしてきた場合、早めに弁護士に相談して、法的対応を視野に入れておくことだろう。学校として問題を共有できていれば現在は「スクールロイヤー」という制度が実施されている。スクールロイヤーとは、学校で起こるいじめや保護者とのトラブル等を法的に解決する弁護士のことで、法律家の立場から相談にのってもらえる。(相談は無料、依頼の申請をしたら翌日には相談にのってもらえる)自分も一度スクールロイヤーに相談した経験があるが、後で訴訟を視野に入れた案件では、弁護士にアドバイスしてもらうととても安心感がある。
学校や教育委員会も組織の防衛のために動き、自分が組織の犠牲になりそうな時は、自分個人で弁護士に相談し、動いてもらうことが必要。一教員は組織の末端に位置する存在なので、末端から何か言っても組織の利益に反することは本気で取り合って貰えないが、弁護士を通せば話は別になる。保護者に対しても同様。費用は少しかかるが自分の味方や相談者をつくる上でも利用すべき存在である。
法が自分の権利を守ってくれる
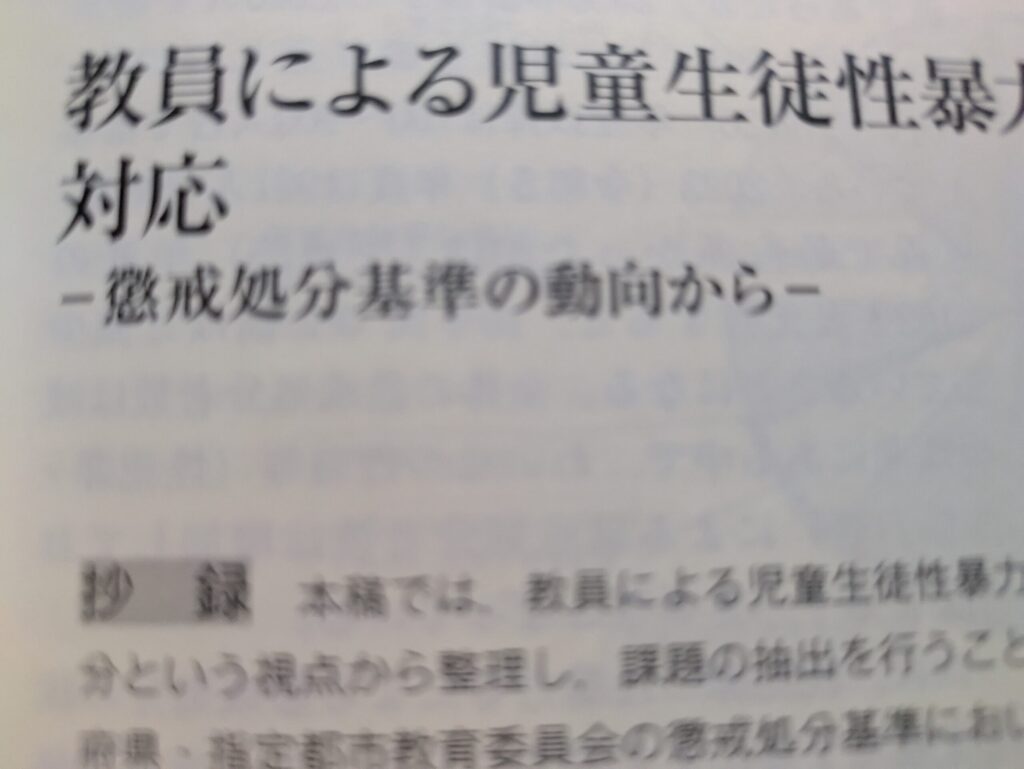
また自分は学校で起きる問題の法的対応を研究する学会の会員になっていて、年に数回、大学に大学教授や弁護士とともに勉強しに行っていた。(最近はあまり行っていませんが、まだ一応会員です)いざという時は法的な根拠が大事で、以外に今起きているようなことと似たような裁判の判例が以前にあったりするもの。また管理職や保護者との会話は相手に内緒でよいので録音しておくことが大事。自分は録音機を2台持っていて保護者と揉めそうなときには必ず録音するようにしてました・・・。(いざという時は自分で自分の身を守るしかない)
嫌な時代ですが、世の中にはとんでもない人が必ずいるので、備えと覚悟は大切です。
学校にも「この通話は、応対品質向上のため、録音させて頂きます。予めご了承下さい。」というメッセージの入る録音機能が付いたコールセンターみたいなところで電話が受け付けられる日がいつかくるのだろうか?