芝山古墳・はにわ博物館へ


成田空港から蓮沼方面に抜ける県道62号線は通称芝山はにわ道とよばれ、道沿いのあちこちに埴輪が置かれている。芝山町は古墳と埴輪を売りにしている町。社会科教員時代に、ここにも一度も来れていなかったので、遅ればせながら多古のあじさい祭りの帰りに芝山町立芝山古墳・はにわ博物館に寄ってみた。ちなみに古墳の形として有名なのは、前方後円墳。この形は独特で大和政権が最上級クラスの人物の墓として位置づけた墳形で、特に重視した地方の有力者にも造営を認めたとされている。そしてこの前方後円墳が一番多く見つかっているのが千葉県。このことから房総地方は大和政権が全国各地に支配を広げていった古墳時代、大和政権が重視した場所であったことがわかる。
古墳が教えてくれる「謎の四世紀」

歴史の授業では、旧石器時代から縄文⇒弥生⇒古墳⇒飛鳥と学習が進んでいく。古墳時代はいつのことになるかというと、大規模な古墳が作られていた3世紀末から6世紀中ごろまでの約350年間。この時期は大和政権が誕生した時期になるので別名、大和時代ともいわれる。時代の流れとしては、邪馬台国の卑弥呼が亡くなった時期から、日本に仏教が伝わって寺院が建てられるようになるまでの時期になる。この時代に、日本ではまだ文字が使われておらず、当時の様子について文字による記録が残っていない。3世紀前半は中国の歴史書(魏志倭人伝)の記録によって邪馬台国や女王、卑弥呼のことなどわかる部分があるのだが、3世紀後半から4世紀にかけては中国も動乱の時期で日本の記録が残っておらず「謎の4世紀」といわれている。このころの社会の様子がどうであったのかの唯一の手掛かりが古墳。そこから出土するもの、特に埴輪が当時の社会の様子を教えてくれる。
騎馬民族が渡来した関東



この芝山の博物館には近くの殿塚・姫塚古墳という前方後円墳から出土した埴輪や副葬品が多く展示されている。まず、展示されている埴輪の人物を見ると、帽子やヒゲ、髪型や服装など何だかユダヤ民族にも似た(ユダヤ人渡来説もある)、とても日本のものとは思えないような雰囲気に感じられるのが特徴。また馬や馬具関係のものも多く、実際に埴輪を見て、埋葬されているこの地域の有力者は、大陸系の騎馬民族だと確信した。日本列島には、縄文・弥生時代には馬、羊、牛、虎などはおらず、突然5世紀に馬の痕跡が表れ始める。 4世紀後半、大和政権は朝鮮半島で高句麗と戦い、そこで高句麗の騎馬軍団の強さをまざまざと見せつけられ敗北した。当時の馬は現在の戦車みたいなもの。そこで朝鮮半島経由で大陸系の馬と飼育や調教を担う渡来系の職人の集団を日本に招き、国産化を進めたのだろう。当時の関東地方は火山灰土で覆われた台地が多く、草原地帯が広がり、馬の放牧と生産に適した土地だったので、そうした馬に関係する多くの渡来系の集団が関東に移住し、勢力を持った。この時期に大和政権は全国にその支配を広げていくが、それを可能したのが東国の馬の存在。大和政権がこの地域を重視し、前方後円墳が数多く存在するのも、この馬がその理由なのだろう。
馬が生んだ武の国
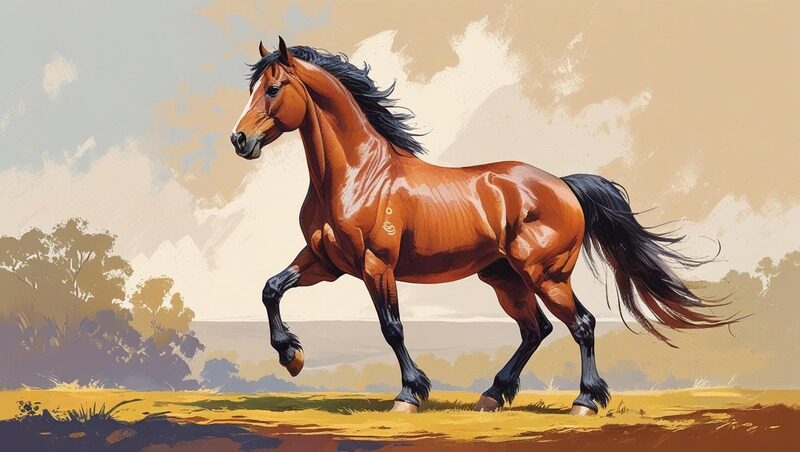
芝山町は、山武郡に属する。山武は昔、武射(ムサ)とよばれた。また今の東京と埼玉は武蔵の国。武(戦う人)と関東地方は繋がりが深い。もともと関東は武(ムサ)の国で、ムサカミ(上)がサガミに、ムサシモ(下)がムサシになったのでないかと思っている。馬が日本に入ってきてから、馬と兵士は切り離せないものになった。なぜなら乗馬の技術、騎乗して弓を操るのは、簡単なことではない。幼い時から長年の訓練を必要とするものなので、馬を生産する関東が同時に兵士を生み出す「武」の場所になったのだろう。歴史を勉強してきて、奈良時代に北九州の守りにつく防人がなぜ遠い関東から行かされていたのか疑問だったが、きっとこのことが理由。その後、関東は武士が生まれ、その末裔である坂東武者が源氏を支え、鎌倉が武士政権の本拠地となり、その後明治維新まで武士政権が続く。関東の歴史は馬なしではうまく(おやじギャグ)語れないのだ。