「主体的・対話的で深い学び」
学校における学習のキーワードは「主体的・対話的で深い学び」である。もちろん、ここでの「主体的」の主語は生徒・児童となる。教育の現場では、教師がこの「主体的」という言葉を盾に色々なことを無責任に生徒任せ、生徒に丸投げにしてうまくいかなかったことを「生徒の責任」「生徒のせい」にしてしまっていることが多い。では「生徒が主体的に学習する」「生徒が主体的に行動する」とはどういう意味を持つのだろうか。
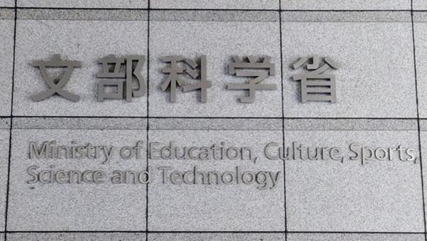
理想を謳う学習指導要領
これがいつも思っていることなのだが、学習指導要領は、勉強が得意なエリートの官僚や学者が考えているので、内容は理想的なのだが、学習が苦手な多い児童・生徒が多い現実に合っていないことが多い。それこそ入試で選抜された学習が得意で能力も備わり、家庭環境にも恵まれた子がそろっている私学の教育ならそれでもよいかもしれないが、普通の公立の義務教育の学校で「周りは強制しないから自分からやる気を出して学習せよ」といって、学習が伸びていく子は半分以下であろう。
ChatGPTに訊いてみた

ChatGPTに「主体的とはどういう意味ですか?」と聞いてみた。答えは「自分の意志や判断に基づいて行動するさま。他人に言われたからやるのではなく、自分から進んで考え、決断し、行動することを指します。」また「主体的と自主的の違いは何ですか?」と聞いてみた。答えは学校の場だと「主体的な学びとは、自分で課題やテーマを見つけ、どう学ぶかを考えて行動する」⇒自分が学びの中心。「自主的な学びとは、先生に言われなくても自分から進んで勉強する。⇒命令されずに動く姿勢。
「主体的」は難しい

今まさに自分は教師の仕事をやめ、それまで組織から与えられていた生徒の教育という使命やタスクがなくなり、組織を離れて、自分個人が社会の中で何をすべきかというテーマを模索し、何をどう学ぶかを考え行動し始めている真っ最中。まさにこれが「主体的」ということだが、考え無しだった自分にはこれがなかなか難しく、闇の中を彷徨っているようで、道筋がなかなか見えない。学習の最終的なゴール地点が「主体的な学び」ならよいと思うが、学習指導要領は保育園や幼稚園を出たばかりの小学1年生から適用されるもの。言ってる内容は素晴らしいのだが、理想が高すぎると感じるのは自分だけだろうか。
「守破離」の教え

「守破離」という有名な教えがある。これは日本の伝統的な芸事や茶道、剣道という世界においての修行の段階をあらわす教えで、物事を学ぶ際の姿勢として昔から受け継がれてきているものである。まずは先人の教えを守るところから始まり、習得できたらその型を破る。最終的には独自に発展させ、型から離れた己のスタイルを確立する。教えの元は能の創始者の世阿弥の「風姿花伝」や千利休の教えを和歌の形にした「利休道歌」の「規矩作法 守り尽くして 破るとも 離るる」に由来すると云われている。ここでの最終的な「離」の段階が、学習道でいえば「主体的な学び」ということになろう。ただ世阿弥も「初心忘るべからず」、千利休も「元を忘れるな」と「離」のフェーズであっても基本の型を大事にすることを説いている。
教師も「主体的」に教育をしなければならない
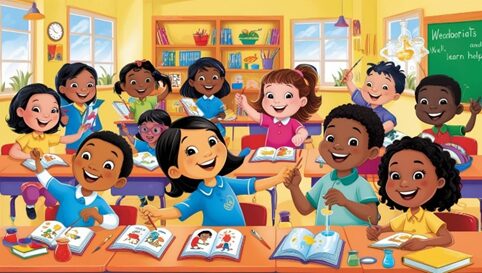
教師が授業での学習や学校生活の場で生徒に基本の型を教えることなく、安易に「主体的」「自主的」という美辞麗句に踊らされ、未熟なこどもにすべていきなり丸投げにして「話し合いなさい」「自分たちで決めなさい」「自分で考えなさい」と言って、結果できないことやうまくいかないことをすべてこどもの責任にしてしまいがちである。「主体性」とは、自分で判断、決定したことに自分で責任を持つという意味合いも含んでいる。全部、生徒のせいにしてしまったら教師の生徒に対す責任(教育の主体性)はどこへ行ってしまうのだろう。教師も「主体的」に活動できる基盤を生徒に授けられているか振り返ってみることも必要なのではないだろうか。