
自分が最初に講師をした船橋市の小学校は、20歳代は自分一人で、30歳代は一人もおらず、40代と50代の職員は半々くらいの年齢構成であった。バブルの時期は地価が高騰し、東京や東京の近郊には普通のサラリーマンでは家を持てない状態だったので、子どももこの地域は大きく減少していて東京に近い葛南や東葛地区では教員の採用もほとんどない時期だったのだ。東京から少し離れたところじゃないと家が買えない状況で、自分が採用された時も千葉県の教職員の採用のほとんどが印旛地区と市原地区であった。印旛地区で自分は採用になったのだが、この地域はバブル期にどっと住宅が増えたため40代、50代の教員はほとんどおらず、バブル期に採用された20代と30代の教員がほとんどという状況で船橋市とは真逆の年齢構成であった。したがって同じ職場で平の教員で定年退職する先生を見たことがなかったし、30代後半の先生がもうベテラン風情で「もう俺は担任はいいよ」とか「部活はもういいよ」といっているような状況だった。まぁ、校内で一番年上になるのだからそういう感じにもなるのであろう。そんな感じなので、50代の先生はたまにいても、担任や部活の顧問を外れるのは当たり前の雰囲気だったのだ。
学校現場の高齢化
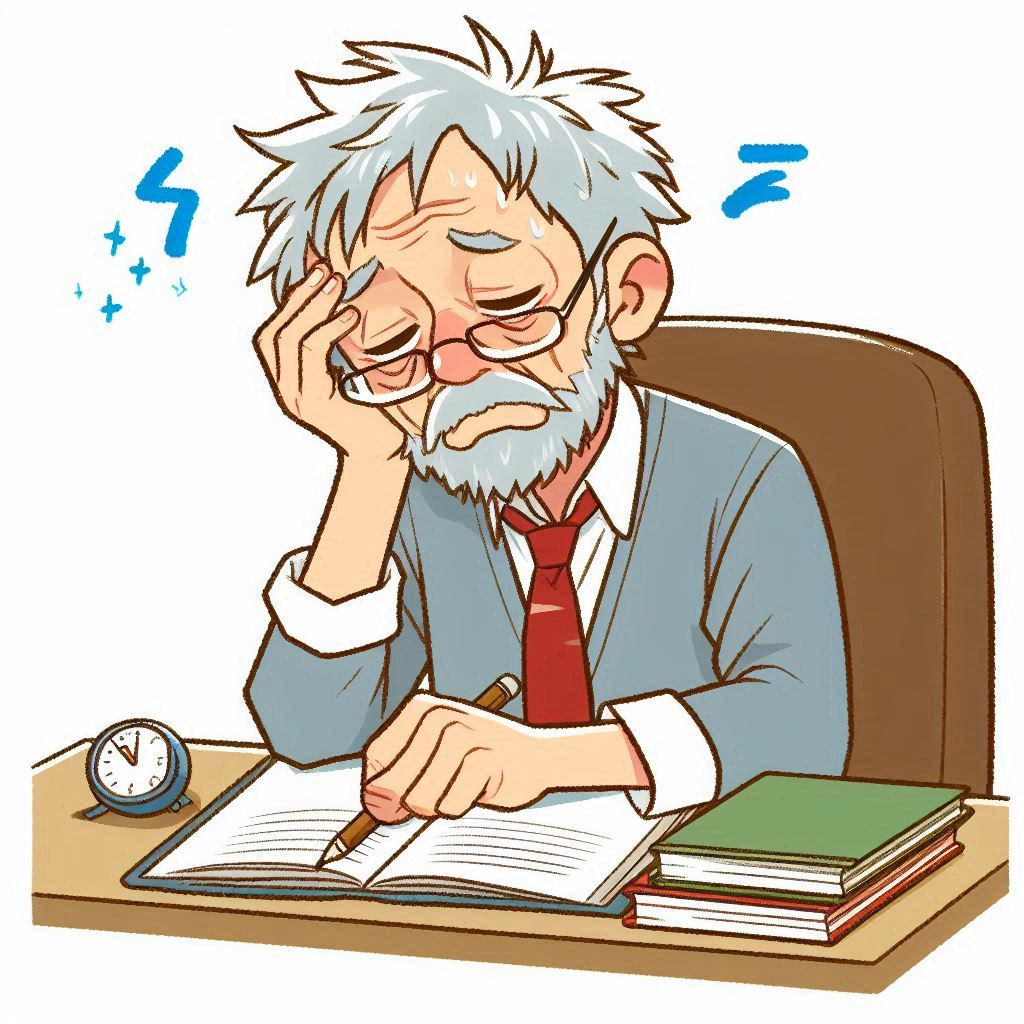
自分が退職前にいた職場は、管理職を除く一般の教員が23人でうち50歳以上が9人という、昔とはまったく違う状況。職員の40%が50歳以上なのだから、50代の教員が老け込んでいては学校が回らないのだが、定年が65歳までに伸び、再雇用制度もあることを考えると、今後さらに校内の高齢化はどんどん進んでいくのではないか。長年の経験と技術があるので授業だけなら問題はない(でも最近のアクティブラーニングやデジタル化にはついていけないかも)のだが、老年期の教員は学級担任や部活の顧問などはやりたがらない人の方が多いのが中学校の実際である。(小学校はまた話が違うであろう)高い給料をもらってんだろといいたくなるが、確かに気力を維持して生徒とバリバリに対峙するのは大変なのである。自分としては仕事を続ける以上、若い先生達にも負けたくないし(今まで頑張ってやってきたプライドもある)情熱を持って生徒に向き合いたい。また「あれはできない」「これはやりたくない」と言うような学校の中でお荷物の存在にもなりたくはない。そう考えると定年の65歳まで勤める自信がなく、金銭面での問題がクリアになるのであれば、自分なりに教育の現場で生徒と向き合い続け、やれることはやってきたという気持ちと後進に道を譲った方がいいのかなという思いになった。
昔の定年退職制度はどうなっていたのか

でも学校制度は明治時代から始まっており、こんな問題は今に始まったことではないのではないかと思い、定年制度について調べてみた。かつては定年は55歳だったいうことも何となく聞いてことがあるが、実際のところはどうだったのか。
調べたところ、55歳定年制という法令は存在しなかった。公務員に初めて定年制度が定められたの昭和60年で、この時に60歳定年制となった。では昭和60年以前はどうなっていたのかというと、55歳前後(女性教員はもっと早かったらしい)になると、退職の勧奨を受け、それに応じると退職金が割増されるのでおおむね57~58歳までに退職していたのだという。いわゆる肩たたきとよばれるものである。その制度の名残が自分も利用した退職勧奨の制度だったのだ。確かにこの制度は現実的なものであったのだろう。50歳を超えて気力がなくなってきたなと思われる人から「肩たたき」をしていけばよいのだから。
現在、定年は60歳から65歳に引き上げられたが、これは65歳が教員としてしっかりと労働できるであろう年齢であるとして設定されたのではなく、年金支給年齢との接続を理由に行われたものである。定年制というのはその年までは雇用が守られるという労働者の権利の問題であるので、退職する時期は制度に決められるものではなく、労働者としての自分が決めるというのが筋であるというのが自分の考えである。もちろんお金のことだけを考えれば権利を行使した方がよいのは当然で、そう考える人を否定するわけではないのだが。